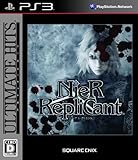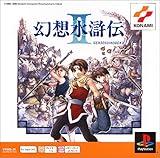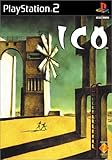吹き溜まり
本や音楽やライブや映画やゲームのこと。
- 2025.07.09 [PR]
- 2010.07.16 『神無き月十番目の夜』/飯嶋和一
- 2010.06.02 『プールの底に眠る』/白河三兎
- 2010.03.11 (゜ーÅ) 積読その2
- 2010.03.09 積読その1
- 2009.05.07 『太陽の坐る場所』/辻村深月
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
『神無き月十番目の夜』/飯嶋和一
 |
神無き月十番目の夜 (小学館文庫) 飯嶋 和一 小学館 2005-12-06 by G-Tools |
水戸城よりの言いつけにて、
常陸の小生瀬に来ていた旧御騎馬衆・大藤嘉衛門。
急な話であった上に、何やら村の様子がおかしい。
どの家も今しがた人が居た気配はするが、
居るはずの家人がどこにも見当たらない。
さらに、かつて嗅ぎなれた戦場の血の匂い…
小生瀬出身と知れた吾助から聞き出した「山林」の地へ赴くと、
嘉衛門を迎えたのは夥しい老若男女の無残な死の散乱だった。
現在絶版にて、入手するには本屋を巡るほか手段のないこの本。
著者の作品としてはお初の一冊目。
かなり前に気に留めていたのをすっかり忘れ、
今年になってふと本屋で背表紙を発見し、購入。
はじめ、時代背景がこんな昔だとは思ってなかった為に、
文章がなかなか読み進められなかったのだが、
波に乗ればもう続きが気になって気になって。。。
物語の構成は、最初に結果が示され、
次に至ったまでの経緯を登場人物の多視点にて綴っている。
結果が出ているからには、読み進めた先に待っているのは
悲劇に他ならない。
家康が天下統一して間もない頃、
武士は名目を失い、刀や鉄砲等の武器は
一介の民の持てる様なシロモノではない。
土地の扱いの改変を受け、各地の民は百姓に徹し、
高い年貢をお納めるべく、日々ひたすらに田を見つめるだけの生活を強いられてた。
かつての騎馬衆として、その力量は名を轟かせ、
それでいて性格温厚にて民からの辛抱も熱い石橋藤九朗。
物語の多くはこの藤九朗とそれに関わる人や状況が綴られる。
先に述べたが、既に結末は明記されている。
読み進めながら、その悲劇を回避できるかもしれないと思われる分岐点があるが、
やはり悪い方へと転がってしまう。
この作品何が凄いって、まるで史実であると錯覚できるほどのリアリティ迫る演出だ。
登場人物のセリフや心情描写が絶妙で、深く掘り下げるほど創作感は高くなり、
かといって表面すぎるとまるで脚本のように感じてしまう。
背景や時代描写も含め、読みながら本当にかの地で、
こんなことがあったんだと思わされる。
戦の悲惨さをしっている肝煎となる藤九朗は、
たとえどんなに生活が苦しくなろうとも、生きてさえいればと自身を抑え、
しかしその藤九朗の願いは村役以下多くの村民には察することできず、
時が流れると共に色濃くなるは惨劇の気配ばかり。
藤九朗、その意を酌んだ者、死の際で自分たちの状況理解した者、
彼らの無念が、果たしてこれは小説の中だけなのか。
大義名分を掲げ、村民全てをなで斬りにした後、
私利私欲と大義名分の核を見失い己が奪った夥しい背後の血で戦慄する者。
歴史に記されなかったこの悲劇が、実はかつて現実であったかと思わされる。
圧倒されました。
『プールの底に眠る』/白河三兎
 |
プールの底に眠る (講談社ノベルス) 講談社 2009-12-08 by G-Tools |
なんて久しぶりな。
これを機に一気に積読を消化したいところ。
この本を手に取ったきっかけは、帯に辻村深月さんを発見した為。
「いつまでも読んでいたかった―辻村深月」(帯より)
んでもってタイトル・装丁共にいいんじゃないか?
ということで購入。
内容は背表紙から以下引用。
夏の終わり、僕は裏山で「セミ」に出会った。
木の上で首にロープを巻き、自殺しようとしていた少女。
彼女は、それでもとても美しかった。
陽炎のように儚い一週間の中で、僕は彼女に恋をする。
あれから十三年・・・・・・。
僕は彼女の思い出をたどっている。
「殺人」の罪を背負い、留置場の中で――。
(『プールの底に眠る』裏表紙より)
タイトルからだとミステリー要素がありそうだが、
実際は少年少女青春物語。
本人曰く、自分は弱いとする主人公の少年。
それでも周りに波風立たないようそれなりの人物を演じながらも、
決して媚びる性格ではなかった彼は、
一般的にいえばやはり強い人間とされるだろう。
決して器用ではなかったし、虐めも受けた。
しかし自分をしっかりもち、逆風でも取り乱すことは選択しなかった。
そんな彼の前に現れた少女<セミ>。
自分が美人であることを全く自覚せず、
周りとは異なる感覚で世界を読み、
それゆえ馴染めぬまま登校拒否状態の少女。
セミとの思い出はたった七日間。
留置場からその七日間を振り返りつつ、
自分と、少女と、取り巻く環境の、
偶然と必然とを今さらながらに想う。
大体の人が予想される展開とは違うと思う。
私はここまでハッピーエンドになるとは思わなかった
詳細は割愛するけども、確かに儚くて綺麗、という感じか。
っていうか、今これ
凄く眠りながらかいているが、まし…
追記
↑寝ました…。
総評としては、綺麗すぎて物足らなかった感が…
最後の事実はスパイスとしては設定はいいかもしれないが、
物語の根っこになってくると微妙な感じが。
私としては霞が晴れたというより、
今までの物語が一気に薄まった印象を受けてしまった。
って今も眠気眼で書いてますが…
『太陽の坐る場所』/辻村深月
 |
太陽の坐る場所 辻村 深月 文藝春秋 2008-12 by G-Tools |
GWにつき帰省中なのだが、本を持ってくるの忘れた…
で、まだこれ買ってなかったので購入、ついでに読了。
辻村さん、彼女の作品はまだ、『冷たい校舎の時は止まる』と
『子どもたちは夜と遊ぶ』の2作品しか読んでない。(でも既出本は全て持ってる)
それでもなんとなく特徴は人物描写とそれを展開する舞台設定かなと。
舞台設定は、基本はこれといって特異なものではないけども、
リアル描写の為に、なるべく現実に即した世界観で行われる物語。
それにちょっとスパイスやら毒やら空虚感やらを加えて、
ありそう、実際あるある、な世界から僅かにズレた世界。
とまぁ個人的に思ってるんだが、
今回の作品、もともと著者の生きた人物描写が私は好きだけど、
その人物描写を抉った作品となっている。
ミステリー要素は無いに等しいかな。
学生時代っていうのは、人間関係はそりゃ色々あると思う。
特に、女なんかはグループを作るし、何かと違うものを排除したがるし。
でもそういうのが表立ってあるのは、中学生くらいまでだと思う。
高校に入るあたりから、それぞれがそういったものを内に秘めるようになるしね。
だから、表立った諍いはないものの、
その代わり秘めた鬱憤はより醜さを増して行く。
そういう中で、如何に自身で消化していくかで、
自分の演じる自分の方向性が象られていく。
上記は自論だけど、
そうやって誰もが一端は感じたことのある感情によって起こった事象を描いた作品が、
今回の作品、『太陽の坐る場所』だと思う。
流石にここまでは…と思う描写でさえ、ギクリとする。
自覚するか否かの違いで、実は皆が心に灯したことのある感情な気さえしてくる。
優しさや、厳しさ、怒り、悲哀、自身の感情がある限り、
完璧な客観的思考なんて不可能だと思う。
世界の中心は、自分。あながちそれは嘘ではない。
感じるのも行動するのも自分でしかないのだから。
物語上気になったのが、それぞれの章で視点を固定して語られているが、
最終的にそれを統合した章かエピローグがあれば良かったかな。
自己解決した彼らが、どうなったのかがちょっと気になった。
面白いかって聞かれると、面白くはないかな…。
そういう作品ではないし。ただただギクリと痛みがくる。